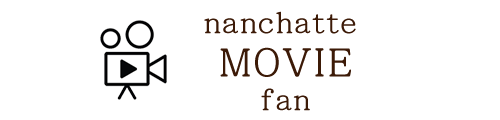目次
作品紹介
2039年のニューヨーク。母親のマヤと娘のゾラは、夫・ダリウスが地球の気候変動を予測して作ったシェルターで暮らしていた。ある日、ダリウスは所用で家を出たきり音信不通となってしまう。ダリウスの帰りを待つ2人のもとに、謎の男女が現れる(2024年)
| 監督 | ステフォン・プリストル |
| 脚本 | ダグ・サイモン |
| 製作 | バジル・イワニク他 |
| 出演 | ジェニファー・ハドソン/ミラ・ジョヴォヴィッチ/クヴェンジャネ・ワリス/サム・ワーシントン |
登場人物
テス(ミラ・ジョヴォヴィッチ)
他のコミュニティからマヤの夫ダリウスの知り合いで、酸素発生器の修理のため、マヤのところにやってくる。
マヤ(ジェニファー・ハドソン)
夫のダリウス、娘のゾラと3人でシェルターに暮らす。夫がいなくなった後、必死にゾラを守ろうとする。
ゾラ(ケクヴェンジャネ・ワリス)
ダリウスとマヤの娘。父がいなくなった後、無線で話しかけ、テスたちを引き寄せてしまう。
父と同じに機器を修理する技術を持つ。
ダリウス(コモン)
マヤの夫でゾラの父。酸素発生器の故障で家族を救うため、自分を犠牲にする。
ルーカス(サム・ワーシントン)
テスト共にマヤたちのシェルターにやってくる。段々と乱暴な部分が露呈してくる。
マイカ(ダン・マーティン)
テスとルーカスの仲間。
感想
舞台が2039年のニューヨーク。地球上の酸素濃度5%。特殊マスクをつけないと外にも出られない。
出たとしても制限時間があり、長くはいられない。
ダリウス、マヤ、ゾラの家族は3人でシェルターで生活している。
最初の時点では他にも誰か人がいるのかはわからないし、どうやってそういう状況になったのかもわからない。
かろうじて、ダリウスがそういう世界を予想して、シェルターをつくっていたことが明かされている。
きっとそういう状況になったときに、ほとんどの人はその時点で死んでしまったのだろうし、生き残ったとしても略奪やら争いなどで、生き残っている人は少ないだろうことが予想される。
けれど、2039年といえば今から数えても14年後。そこまで遠い未来ではないことが怖い。
今でも地球温暖化や自然破壊、戦争などの状況を考えれば容易にイメージできる世界なのかもしれない。
そして呼吸さえもままならない世界。
こういう系のドラマや映画は数あるけれど、呼吸できない系は観てるこっちも息苦しくなってしまう。
世界観はわかるけれど、ストーリーとしては物足りない
ミラ・ジョヴォヴィッチといえば、「バイオハザード」シリーズで一世風靡した大人気女優。
他にもジェニファー・ハドソンやサム・ワーシントンなど有名俳優が出演しているにもかかわらず、なんだかまとまらない感じに思えた。
3人の生活からダリウスがいなくなり、親娘の二人の生活の中で、突然、テスとルーカスがやってくる。
もちろん、警戒しないわけにはいかない。
荒廃したした世界で、同じ人間といえど信用できるわけがない。
二人は他のコミュニテイから来て、酸素発生器が故障して使えなくなるまえに、マヤたちの発生機を参考に修理したいから、見せてくれという。けれどマヤたちは二人が信用できず、二人を縛り上げるが、そこにもう一人マイカが現れ、ドアを開けたところに入り込む。
すぐさまマイカを縛るマヤ。
そして、マヤとゾラ、テスとルーカスの攻防が始まるのだけれど、これがなかなかラチがあかない。
どちらも軍とかではないし、一般人どうしだから、銃は使うけれどそこまで本格的な銃撃戦でもない。
けれど映画の半ばまでそれがダラダラと続く。
ドキドキハラハラではなく、ダラダラと続いてしまって話に緊張感がなくなってしまっている。
マヤは頑なにテスたちを信用しないし、テスは何とか信用してもらいたいと思っているけど、段々とマヤの頑なさにイライラしてきて武力行使になっていく。観ている方もイライラしてきて、「これは一体いつまで続くんだ」と呆れてしまう。
マヤの気持ちはわかる。マヤにはゾーラという守るべき娘がいて、遠くにいる大勢のコミュニティの話が本当なのかわからないし、テスやルーカスを信じるに足るものが何もない。
外で生活ができないわけだから、何が何でもシェルターを奪われるわけにはいかないのだ。
なんだかんだでシェルターの中に入るためのキーが必要になり、それはダリウスが死んだ場所まで行かないといけないということで、マヤとテスが車で向かう。
そこには、シェルターの酸素発生器が故障し、二人しか生きられなくなったということで、時間稼ぎのために自分が犠牲になったダリウスの遺体があった。
キーは見つかったものの、シェルターでは二人しか生きられないし、発生機を直さない限りずっとは生活できないのことをマヤがテスに打ち明ける。
足をけがして動けなくなったマヤ。車も動かず、必ず迎えに来ると約束してテスは途中で自転車を拾い、急いでシェルターに帰る。
キーでシェルターの中に入ったテスとルーカス。中にいたゾラを縛るが、テスがルーカスにこのシェルターでは二人しか生きられないことを言うと、ルーカスはあっさりゾラを殺して、急に壊れた人間のように凶悪さを露呈していく。
ここまであまり盛り上がりもなく、あっけなく殺されてしまうならば、テスがミラ・ジョヴォヴィッチである必要があったのか。
ルーカスを演じるサム・ワーシントンも、さすがの演技ではあるが、急に壊れてしまったように残酷な殺人者になってしまう。
けれど、逆にこれが現実的なリアルなのかもしれない。
一度帰ってきたテスだが、約束通り、マヤを助けに戻ろうとする。
テスが人間の「善」であるならば、それを制止して、生きるために人をも殺してしまうルーカスは人間の「悪」なのか。
けれど、こういう世界では何が「善」で何が「悪」なのかがわからなくなってしまう。
こういう映画やドラマで描かれるのは、得てして人間の恐ろしさ。
「生きるため」に手段も選ばない集団が必ず発生して人々を支配しようとする。
「ロード・オブ・リング」のヴィゴ・モーテンセンの「ザ・ロード」でも、大災害で文明が失われ、空は塵に覆われ寒冷化が進み動植物は死滅する。人は自殺するか餓死するか、お互い殺し合い、その死骸を食べるしかない、という壮絶な世界が描かれていた。
弱いものは殺され、食べられる。考えただけでも恐ろしいけれど、そんな世界で生きていくには「善」も「悪」もなくなって、ただ「生きる」ことだけが目的になる。
そういう意味ではこの映画「ブレス」は、そういう本格的サバイバルスリラーとしても今ひとつな感じがしてしまった。
最後にはマヤとゾラはテスたちが言っていたコミュニティに行き着き、そこで酸素発生器を直し、明るい未来に向かって一歩ずつ前に向かっていく、というハッピーエンディングなのはいいのだけれど、そこまでのストーリーがなんだか中途半端感は否めない。
現実でも、いつかはこんな世界になってしまうのか。
こんな荒廃した世界になったとしても、人々が協力し助け合っていく未来ではありたい。