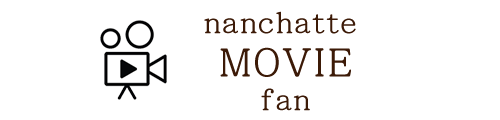1940年、第二次世界大戦下のロンドン。男性が次々と徴兵されるなか、コピーライターの秘書・カトリンは、プロパガンダ映画の脚本家としてスカウトされる。
だが製作が始まると、厳しい検閲や軍部からの横やりなど、脚本が二転三転するトラブルが続出し…。( 2016年)
作品紹介
| 監督 | ロネ・シェルフィグ |
| 原作 | リサ・エヴァンス |
| 脚本 | ギャビー・チャッペ |
| 製作 | スティーブン・ウーリー/アマンダ・ポージー/エリザベス・カールセン |
| 出演 | ジェマ・アーマートン/サム・クラフリン/ビル・ナイ/ジャック・ヒューストン ヘレン・マックロリー/エディー・マーサン/ジェイク・レイシー |
登場人物
カトリン・コール(ジェマ・アータートン)
コピーライターの秘書だったが、バックリーのスカウトで映画の脚本を女性の視点から書くことになる。
最初は戸惑いながらも、次第にその才能を開花させていく。
同棲しているエリスと結婚していないのに「既婚者」と周りに言いつつも、結婚指輪は自分で買っているカトリン。エリスの描いた絵の中の小さな自分の姿に不満もありながら、自分の道を見つけ出そうとする女性を演じたのはジェマ・アータートン。
「ボヴァリー夫人とパン屋」、「007慰めの報酬」でボンドガールを演じ、海外ドラマ「テス」では主人公を演じた。
トム・バックリー(サム・クラフリン)
プロパガンダ映画を撮ることになり、女性のセリフを女性の視点で、ということになり、カトリンを抜擢する脚本家チームのチーフ。皮肉的な会話が多いが、カトリンの才能を評価し、その魅力に惹かれていく。
ワタシの大好きなサム・クラフリン。サムの映画の中でも好きなキャラクター。
「世界一キライなあなたに」や「あと1センチの恋」とはまた違う魅力が。恋が実る前の切ない表情もいい!
合わせて読んでみる
『世界一キライなあなたに』感想/ロマンスの中にも人生の選択を問う
職を失った26歳のルーは、バイク事故に遭い車椅子生活を送る青年実業家・ウィルの介護役兼話し相手として採用される。献身的なルーにウィルも頑なだった心を開き、2人は心を通わせるように。だが、ルーはウィルがある重大な決意を秘め […]
アンブローズ・ヒリアード(ビル・ナイ)
ベテランの映画俳優。自意識過剰で過去の人気作品でスター気取り。
脚本に文句を言ったりしてカトリンを困らせる。
ベテラン俳優の「あるある」な感じを見事に演じたビル・ナイは、役どころと同じくイギリスのレジェンド俳優。
「パイレーツ・オブ・カビリアン」や「アバウト・タイムー愛おしい時間についてー」など多数。
黒澤監督の「生きる」のリメイク「生きるLIVING」ではアカデミー主演男優賞にノミネートされた。
エリス・コール(ジャック・ヒューストン)
画家でカトリンの内縁の夫。夫と言っても結婚はせず、結婚指輪もカトリンが自分で買ってつけているというだけ。
スペイン内戦で片足を失っている。
サミー・スミス(ヘレン・マックロリー)
ヒリアードのエージェント。落とされた爆弾で死んでしまう。
ソフィー・スミス(クロエ・ピリー)
サミーの姉。サミーの死後、ヒリアードのエージェントを引き継ぐ。
感想(ネタバレアリ)
1940年代のイギリスは戦争真っ最中。いつ爆弾が落ちてくるかわからない、まさに死と隣り合わせの生活。
そんな中でも人々を楽しませるいい映画を撮りたい映画人たちが、力を合わせてなんとか映画を完成させようと奮闘する姿が心に響く。
プロパガンダ映画の製作に女性の視点を
作るのは、実際にあった「ダンケルクの戦い」で兵士を救った双子の女性たちの物語。そこで、男ばかりの映画製作に女性の視点を取り入れるため、バックリーはカトリンを脚本家チームに抜擢する。
最初は「秘書」と思っていたカトリンだが、バックリーや周りのフォローもあり、その才能を発揮していく。
時代背景もあるだろうし、才能もあるだろうけれど、「女性の視点」で「女性のセリフ」を書かせるという発想があることが、よりいいものをつくりたいという映画人の臨機応変さというか、それはすごいなと思った。
その一方で、一緒に棲んでいるエリスはカトリンを認めていない。
それどころか、エリスはカトリンに生活するお金がないからウェールズに帰れと言う。
それでもカトリンはエリスと別れず、必死に二人の関係を修正しようとする。
映画の方は製作が決定し、脚本家チームが始動。
バックリーと脚本パートナーのパーフィットの掛け合いが楽しい。
脚本ってこんなふうにイメージを練って作っていくのか。そこにセリフを入れていく。
基本的には「事実を元に」のはずだけれど、バックリーは言う。
たとえ事実と違っていても
「これが映画だ。現実から退屈な事実を削る。」
「事実と真実は違う。何よりもストーリーが優先。」
そうだよな~。。。事実をそのまま映像にすることのほうが難しいのかもしれない。
けれど、脚本のつくりかたの一端がみえて面白い。
「ダンケルクの戦い」とは
第二次世界大戦、ドイツ軍は戦車や航空機を駆使した電撃戦を展開、新戦法によってフランス軍とイギリス軍を中心とした連合軍主力の後方を突破すると、ドーバー海峡まで駆け抜けてこれらを包囲し、ダンケルクへ追い詰めた。
イギリスの首相ウィンストン・チャーチルは、イギリス海外派遣軍とフランス軍からなる約35万人をダンケルクから救出することを命じ、イギリス国内から軍艦の他に民間の漁船やヨット、はしけを含む、あらゆる船舶を総動員した撤退作戦(作戦名:ダイナモ作戦)が発動された。撤退作戦に参加した船は900隻にのぼった。(wiki参照)
映画鑑賞報告『人生はシネマティック!』(2016) pic.twitter.com/pbbK0g0vrg
— Satoshi_M (@goat_yaroh) February 10, 2024
コメディあり、ロマンスあり
こうやって映画を作っていくんだという一端がみえて、あらためて映画は俳優だけでなく、監督、脚本、照明、小道具、大道具、たくさんの人に支えられ出来上がっていくということを感じられる。
映画の魅力は実は、出来上がるまでが一番苦しく、また楽しいのかもしれない。
ヒリアードが何かにつけて監督や脚本に文句を言ったり、アメリカの要請でアメリカ人の、いかにもヤンキーな戦争の英雄を映画に出させたり、そのアメリカ人が大根役者で作品を台無しにしそうになったり。。。
作り手側には大問題だけれど、観てるこっちは笑ってしまう。
その当時の映画作りの難問を乗り越えて作り上げていく過程が垣間見れる。
また、カトリンとバックリーのロマンスも。
カトリンはバックリーに惹かれながらも、エリスと何とかやっていきたいっぽかったけれど、エリスが他の女性と浮気している現場をみて、別れる決心をする。そしてバックリーの元へ。
でも、そこでもバックリーもカトリンも素直になれずケンカ別れみたいになってしまい、脚本が書けなくなってしまうバックリー。
その切ない表情のサム・クラフリンがたまらん・・・
でも、「戦時中」のため、明日をもしれない日々。昨日一緒に笑っていた人が今日は亡くなるという現実も。
意を決して仲直りのメッセージを脚本風に書いてバックリーの机に置くカトリン。それはカトリンからバックリーへの愛の告白。
脚本風に書くというのが洒落ていて、お互いに同じ価値観だからこそ、心に響く。
一瞬で変わってしまう現実
やっとお互いの気持を伝え合ったというのに、その瞬間、バックリーは映画に使われていた大きな土台が崩れてその下敷きになってしまう。正直、「サム、また死ぬ役かー」とガックリきてしまったけれど、人が死んでしまうというのは、こんなにも一瞬のことなんだと。
以前、仲間の孫が休暇中に交通事故で死んだと聞いたとき、カトリンが
「無意味な死は余計につらいでしょうね」と言う。
戦争中で、兵士でもあるけれど、戦争ではなく交通事故で亡くなったことに対しての言葉。
そこでバックリーが答える。
「死に意味はないよ。
なぜ人は映画が好きか?構成されてるからさ。
ストーリーには形、目的、意味がある。不幸な展開も作為的で意味がある。
人生とは違う。」
人生には意味がないという例えなのかと思うと切ないけれど、死に意味を持たせたいと思うのは、残されたものの慰めのためなのかもしれない。たとえ戦時中に戦争や爆撃で亡くならなくても。
バックリーがやっとカトリンと気持ちを通じて、きっと二人は結婚してお互いになんだかんだと言い合いながらも、良きパートナーとして共に歩んでいくんだろうなと、安易に想像できる。けれど、それは、その次の一瞬で打ち消されてしまう現実。
戦争で死んだわけではない。爆撃で死んだわけでもない。
人はいつかは死ぬと思っているけれど、それが「今」とは思っていない。
けれど、それは誰にもわからなくて誰にも起こり得ることなのだ。
「死に意味はない」と言ったバックリーの言葉が余計切ない。
再び前を向いて
悲しみに打ちひしがれるカトリンは、家にこもりきりで映画も観られない。
ヒリアードに次回作の脚本を打診されるが、悲しみが癒えないカトリン。
それでも、映画を見るべきだというヒリアードの言葉に映画を観に行き、そこで映画の世界に没入する人たちを観て前を向く決心をする。
映画には人生を変えるものがある。
人は映画を観て、その世界でヒーローになったり、ヒロインになったりしている。
「ダンケルク」の映画でも、全てが事実ではなくても、ローズとリリーがダンケルクの兵士の救出に向かったことは事実だし、それが映画になったりするわけで、「人生」と「映画」は違うと何故言えるだろう?
自分が「普通」と思っていることは、もしかしたら「普通」ではないかもしれないし、もしかして「映画」にすれば劇的な人生に描かれるのかもしれない。
カトリンはバックリーの机とバックリーのタイプライターで次回作を書く。
きっとバックリーと二人で書いているんだと思いたい。